室内や庭で放し飼いにでもしない限り、爬虫類・両生類の飼育にケージは必要不可欠です。
しかし、種類が多いので一体どのようなものを用意すれば良いのか、初心者の方は迷ってしまうかもしれません。
ペットにとってケージは大切なお家です。
飼育する生き物に合っていないケージを選んでしまうと、以下のようなトラブルの原因になります。
- ペットが脱走してしまう
- メンテナンスがしにくい
- 飼育環境をうまく作れず病気の原因となる
今回は爬虫類・両生類の飼育に使う一般的なケージの種類と選び方のコツをまとめてみました。
新しくペットをお迎えする際に参考にしてみてください。
ケージの材質
爬虫類用のケージの材質はプラスチック・ガラス・アクリルの3種類が主流です。
メインのケージとしてはガラスケージを選んでおけばまず間違いありません。
また、サブとして安価なプラケースを数個持っておけばいざという時に重宝します。
プラケース

プラケースはその名の通りプラスチック製のケージです。
略してプラケと呼ばれることもあります。
サイズは40cm未満で、上部にメッシュの蓋がついているものが多いです。
プラケースのメリット
プラケースはガラスやアクリルに比べると軽く、床材交換・水換えなどのメンテナンスがしやすいのが利点です。
また、価格も非常に安く、百均などでも購入することができます。
プラケースのデメリット
プラケースは柔らかい材質のため傷がつきやすく、1年も使えば表面が白くなりケージ内の確認がしにくくなってしまいます。
そうでなくても劣化しやすい材質のため、長期的な使用には不向きと言えるでしょう。
プラスチックのため熱にも弱いです。
保温球や紫外線ライトは構造的に取り付けるのが難しく、暖房器具を取り付けるとしてもせいぜいパネルヒーターくらいが限界です。
こんな時に使おう!
プラケースは特大サイズでもせいぜい幅50cm程度までが限度です。
そのため、小型で運動量の少ない生き物の飼育に向いています。
掃除の際のペットの避難場所やエサやりスペースとしての活用もおすすめです。
- とにかく安く購入したい
- サブのケージとして使用する
- 比較的小型・高温環境が必要にならない爬虫類の飼育
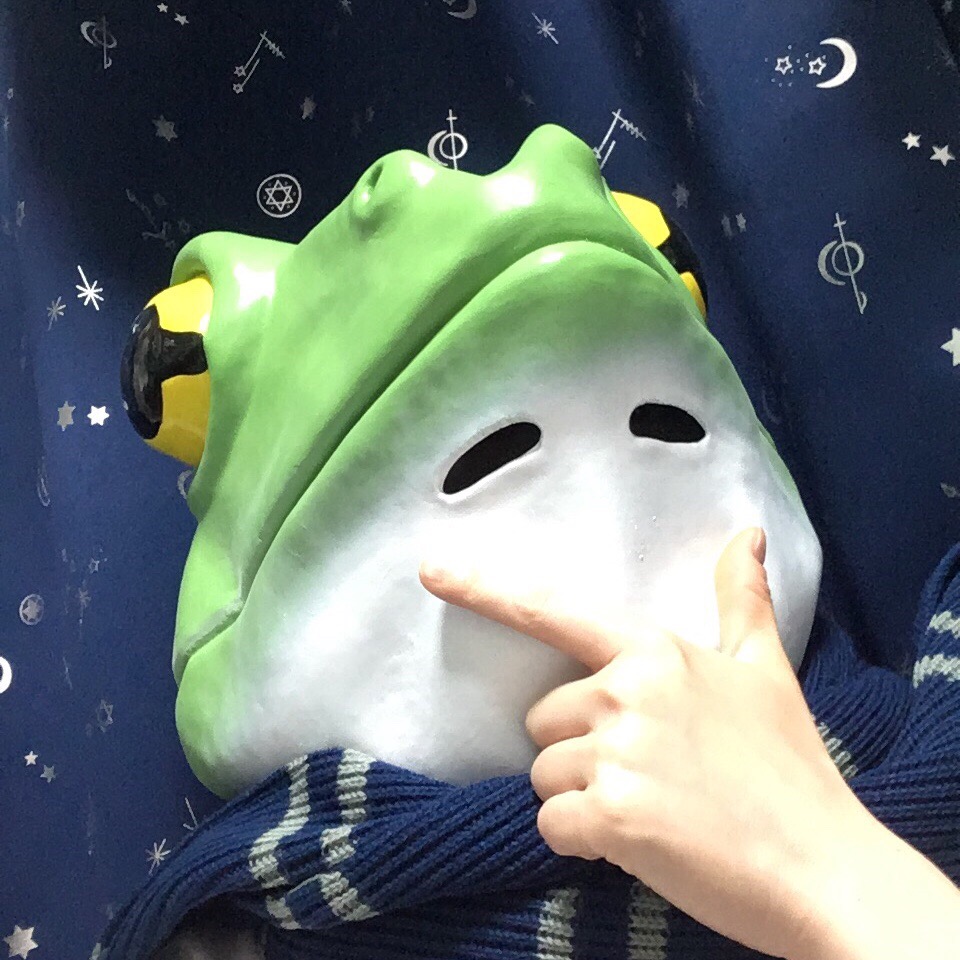
エサ用のコオロギなどの飼育にプラケースを使っている人も多いです。
ガラスケージ

ガラスケージは、爬虫類用のケージとしては最も主流だと思います。
サイズ展開も豊富で、15cm未満の超小型から120cm以上の特大まであります。
鍵付きのものや全面に扉がある観音開きタイプのものなど形状も多種多様で、飼育する爬虫類の種類に合わせて選びましょう。
ガラスケージのメリット
ガラスケージは傷がつきにくいため視認性に優れています。
価格は安くはありませんが、長期的に使っても劣化しにくいため買い替えの頻度は低く、コスパは高い材質だと思います。
ガラスケージのデメリット
ガラスケージの最も大きなデメリットは重さと割れやすさです。
ケージだけでも結構な重さがあるのに、ここに床材や水を入れるとさらに重くなり動かし辛くなります。
無理をすると落として割れてしまうこともあるのでメンテの際には注意しましょう。
こんな時に使おう!
大型の爬虫類を飼育する場合は、メンテの際にケージごと動かすことはないためガラスケージでも問題はないでしょう。
むしろ大型のプラケースやアクリルケージはなかなか売っていないため、特注や自作でもしない限りほぼガラスケージ一択になると思います。
ガラスは熱にも強いため、常にヒーターや保温球をつけておかなければいけない砂漠・熱帯地域の爬虫類の飼育にも向いています。
- ケージの形状にこだわりがある
- 頻繁にケージを動かすことがない
- 中型~大型・高温環境が必要な爬虫類の飼育
アクリルケージ

アクリルケージはガラスケージと同じかそれ以上の耐久性を持ちながら、軽量でもある素材です。
同じサイズ・厚みのガラスケージと比べた場合、アクリルケージは約半分の重量だと思います。
爬虫類用として販売されているアクリルケージはサイズ展開も少なく、小型爬虫類向けのものしかありません。
プラケースの上位互換のような感じでしょうか。
上部に穴の開いたスライド式の蓋が付いている商品が多いです。
アクリルケージのデメリット
デメリットはプラケース同様に熱に弱いこと、また、ガラスに比べて傷もつきやすいことです。
こんな時に使おう!
プラケースでは心もとないけれどガラスは重くて扱いにくいという場合はアクリルケージがおすすめです。
- 耐久性と軽さのどちらも欲しい
- 多少の傷は気にしない
- 比較的小型・高温環境が必要にならない爬虫類の飼育
ケージの形状
飼育する爬虫類によって向いているケージの形状も違います。
※呼び名は私が勝手につけているだけで、一般的な名称というわけではありません。
横型タイプ

高さよりも横幅が広いケージです。
地上を這うタイプの爬虫類に向いています。
鑑賞魚用の水槽も横長タイプのものが主流です。
これは、魚類は上下の移動よりも横方向の動きの方が多いためです。
ヒョウモントカゲモドキ、フトアゴヒゲトカゲ、カメ、イモリ、ウーパールーパー など
縦型タイプ

横幅より高さのあるケージです。
野生では地を這うこと少なく、木の上などで生活する爬虫類・両生類の飼育に向いています。
ヤモリ、カメレオン、ツリーフロッグ など
キューブタイプ

高さ・横幅・奥行がほぼ同じ長さのケージです。
キューブタイプのケージの多くは30cm未満で、ほとんど動きのない生き物の飼育に向いています。
ツノガエル、バジェットガエル、ベタ など
我が家の爬虫類・両生類のケージ紹介
我が家で実際に飼育に使用しているケージの紹介です。
どれも使用を開始して1年以上経っているので、使用感など参考にしてもらえればと思います。
トップテラ TOP-120×45×45

マルギナータリクガメのかめおの飼育に使用しています。
値段は高いですが、120cm以上のケージはなかなかないのでありがたいです。
前面の扉部分の2枚のガラスは取り外せるので、引っ越しの際には外して段ボールに包んで運んでもらいました。
設営の際に少し無理をしてしまい、底面の黒いプラスチップ部分の角が少し欠けてしまいました…。
それでも全然使えているので問題はないのですが。
だいぶ前に購入したので記憶があいまいですが、おそらくランプステーは付属していなかったと思います。
グラステラリウムはデフォルトでランプステー付きなので、そこは少し残念でしたね。
試しにグラステラリウム付属のランプステーを付けてみましたが、段差の高さが異なるようで互換性はありませんでした。
トップクリエイトの公式サイトを見るとランプステーは別売りであるようですが、Amazonなどのネットショップで売ってるのを見たことがなく未だ入手できず…。
蓋はメッシュになっていて、1枚ではなく左右の2枚に分かれています。
なので、蓋を1枚外してライトの取り付け位置を確保しました。
残した蓋の方には暖突も設置しています。
EXOTERRA グラステラリウム3045

クレステッドゲッコーのヤモちゃんの飼育に使用中。
グラステラリウムはさまざまな形状のものが発売されていますが、クレスの飼育なら3045が良いかなと思います。
ショップでも同じものを使用して展示していましたね。
観音開きなのでエサやりなどのお世話がしやすい!
蓋にコード穴が付いているので、ライトや暖房器具の設置にも向いています。
我が家ではクレスケージにはミスティングシステムを導入しているので、チューブはここから通しています。
蓋はメッシュタイプです。
蓋だけでなく全面の扉下の部分にも換気孔があるので、蒸れに弱い生体の飼育にも向いています。
グラステラリウムはバックグラウンド付きなので、これに流木などを適当に入れるだけで良い感じの見栄えになるのも良いところ。
グラスゾーン 20WH

クランウェルツノガエルのケロちゃんの飼育に使用しています。
先代のケロちゃんの時はプラケースを使用していたのですが、やはり傷が目立つということで当代からはガラスケージに変えました。
ガラスは確かに重い…ですが、我が家はソイル飼育なので床材交換の頻度は高くなく、それほど世話が大変になったなとは感じません。
蓋はメッシュのスライド式。
これが非常に良くて、ケロちゃんが飛び跳ねてぶつかってもうっかり蓋が開いてしまう心配がありません。
以前使用していたプラケースは蓋がパカっと開くタイプだったので、下からの衝撃には弱かったんです。
ツノガエルは意外と力が強いので、力業での脱走ができないというのはかなりありがたいですね。
ケロちゃんはオスなので20cmで問題ないですが、大型のメスに使用するには30cmのグラスゾーン 30WHの方が良いと思います。





コメント