読み:しきさいへんい
爬虫類・両生類のモルフを語る上で色彩変異は必修と言っても過言ではありません。
どれもカタカナのややこしい名称がつけられていますが、覚えておくと生体購入やブリーディングの際に役立ちます。
色素の種類
動物の色素は黒色色素・赤色色素・黄色色素の3種類があります。
この3種類の色素がどのような比率で発現するかによって体色に変化が生まれるわけです。
青や緑の動物もいるじゃないかと思うかもしれませんが、実は青色色素を作れる脊椎動物はほとんどいません。
青や緑の体色の生物の多くは、光の反射によって青っぽく見せているだけなんです。
色素欠乏
アルビノ系
アルビノはメラニン生成のできない個体、つまり黒色色素欠乏のことを指します。
アルビノ個体は黒色色素をもたないため赤目になるのが大きな特徴です。
アルビノの目が赤くなる理由として、「黒が抜ければ赤と黄が残るため」と説明されることがありますが、これはちょっと違います。
なぜなら、赤色色素をもたない個体も赤目になるからです。
赤色色素がないのになぜ目が赤くなるのか?
それは毛細血管の色が透けて見えるためです。
血液の赤色は赤血球に含まれるヘモグロビンによるものなので、赤色色素の有無は関係ありません。
アルビノ
| 黒 | × | 赤 | — | 黄 | — |
|---|
前述したように、アルビノは黒色色素の持たない色素欠乏の総称です。
アルビノと言うと白いイメージがありますが、実際には体色が真っ白になるとは限りません。
黒色色素がなくても、赤色色素や黄色色素は正常に発現している場合もあるためです。
爬虫類・両生類のアルビノとして販売されているもので真っ白い個体はほとんどおらず、薄い黄色やオレンジなどの体色をした個体が多いように感じます。
岩国のシロヘビ

山口県岩国市に生息するシロヘビはアオダイショウのアルビノ個体です。
アルビノは野生では目立つため捕食されやすく、また、視力に問題があることも多いため生存に不利だと言われています。
岩国のシロヘビのように野生環境で何世代にも渡ってアルビノ形質が失われず定着している例は、世界的にも非常に珍しいケースです。
アメラニスティック
| 黒 | × | 赤 | — | 黄 | — |
|---|
略称:アメラニ
アメラニスティックは黒色色素をもたない色彩変異です。
そのため、単語そのものの意味としてはアルビノと同じということになります。
ただ、やはり一般的にはアルビノ=白い、というイメージが強いですよね。
そのため、アルビノ個体でもあまり白っぽくないものはアメラニスティックと呼び分けていることが多いように感じます。
例えば、コーンスネークの黒色色素欠乏個体は赤色が強く現れます。
これをアルビノとして販売すると、「白くないのに!?」とびっくりする人もいるかもしれません。
しかし、アメラニスティックとして販売すれば一般的なアルビノのイメージは持たれないので、「ただ黒が抜けただけの個体なんだな」と理解されやすいです。
レッドアルビノ
| 黒 | × | 赤 | ○ | 黄 | — |
|---|
アルビノのうち、赤みの強い体色をしている個体をレッドアルビノと呼びます。
前述のアメラニスティックとほぼ同じような使われ方をしますので、どちらの呼び名を採用するかはショップやブリーダー次第といったところでしょうか…。
ただ、アメラニスティックが赤色色素・黄色色素の有無を問わないのに対し、レッドアルビノは明確に赤色色素がある個体のことを指すので、言葉そのものの意味としては明確な違いがあります。
その他
アネリスリスティック
| 黒 | (○) | 赤 | × | 黄 | — |
|---|
略称:アネリ
赤色色素をもたない色彩変異です。
体色は黄色色素のあるものはくすんだ茶色、黄色色素のないものはグレーっぽくなります。
アルビノと同時に発現することもありますが、その場合にはアネリスリスティックではなく単にアルビノと呼ばれることの方が多いです。
そのため、必然的にアネリスリスティックは黒色色素のある個体を指す場合が多いです。
アザンティック
| 黒 | (○) | 赤 | — | 黄 | × |
|---|
略称:アザン
黄色色素をもたない色彩変異です。
体色は赤色色素のあるものはやや茶色、赤色色素のないものは白黒のモノトーンに近くなります。
こちらもアルビノと同時に発現した場合にはアルビノ・レッドアルビノなどに分類されてしまうため、必然的に黒色色素のある個体を指す場合が多いですね。
色素減退
色素減退は特定の色素の生成量が少なくなる個体です。
アルビノのように特定の色素の生成がまったくできなくなるわけではないため、基本的に目は黒くなります。
色素減退は「ハイポ○○」という名前で呼ばれることが多いですが、このハイポ(hypo-)には「低い」「少ない」などの意味があります。
ハイポメラニスティック
| 黒 | △ | 赤 | — | 黄 | — |
|---|
略称:ハイポ
黒色色素の少なくなる色彩変異個体です。
一般的にハイポとだけ言う場合にはハイポメラニスティックを指すことが多いです。
黒色色素が少なくなることで彩度が高まり、体色が鮮やかに見えやすくなります。
体色だけ見るとアルビノによく似ていますが、ハイポメラニスティックの場合には目は黒くなります。
ハイポエリスリスティック
| 黒 | — | 赤 | △ | 黄 | — |
|---|
赤色色素の少なくなる色彩変異個体です。
ハイポザンティック
| 黒 | — | 赤 | — | 黄 | △ |
|---|
黄色色素の少なくなる色彩変異個体です。
リューシスティック
| 黒 | △ | 赤 | △ | 黄 | △ |
|---|
略称:リューシ
リューシスティック=白化です。
全ての色素の生成量が少なく、体色が白っぽくなる色彩変異をリューシスティックと言います。
アルビノと混同されることが多いですが、リューシスティックとアルビノはまったくの別物です。
アルビノは色素が生成できないため仕方なく白っぽくなる個体、リューシスティックはあえて色素の生成を抑えて白くしている個体といったイメージです。
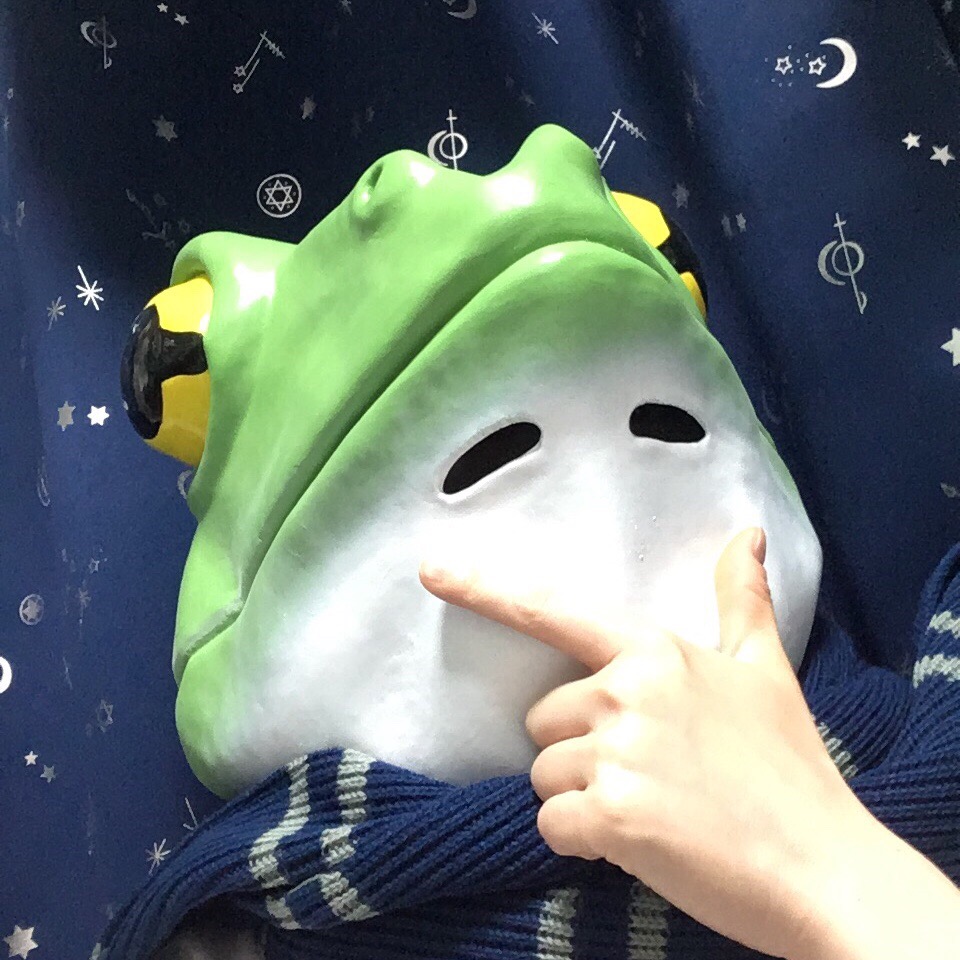
自然界では色のある個体よりもリューシスティックの方がメジャーとなっている生き物も多いです。
例えば、ホッキョクグマ、ハクチョウ、シロイルカなど。
色素増加
色素減退とは逆に、特定の色素の生成量が多くなる色彩変異もあります。
色素増加個体は基本的には黒色色素があるため彩度は低めで濃い体色になりやすく、力強さやかっこよさを感じるモルフが多いイメージです。
メラニスティック
| 黒 | ◎ | 赤 | — | 黄 | — |
|---|
黒色色素が強く発現する色彩変異です。
特に黒色色素の多い個体は模様などもあまりわからず、ほぼ真っ黒な状態になることもあります。
エリスリスティック
| 黒 | — | 赤 | ◎ | 黄 | — |
|---|
略称:エリスリ
赤色色素が強く発現する色彩変異です。
ザンティック
| 黒 | — | 赤 | — | 黄 | ◎ |
|---|
黄色色素が強く発現する色彩変異です。

